育児は、仕事と比べて楽なものだと思っていませんか?
-150x150.jpg)
仕事で疲れているから、家ではゆっくりしたいなぁ。
そう思っているパパもいるでしょう。
でも、ママだって休む間もなく育児と家事を頑張っています。
仕事と育児では、大変さの”質”がまったく違うのです。
「どちらが大変だ!」と張り合うのではなく、お互いの負担を認め合って協力していくことが大切です。
仕事と育児で、うまく心のバランスが取れていない新米パパ、そしてママにとっても役立つ記事になっていますので、ぜひご覧ください。
🖊️この記事でわかること
はじめに
「仕事と育児どちらが大変なのか」
これはよく議論になるテーマです。

育休が終わったら、全然家事と育児をしてくれない。
-150x150.jpg)
帰宅してからも育児をしているのに、なんで認めてくれないんだろう。
このように、気持ちがすれ違っている夫婦は少なくありません。
ではまず、世間一般における「家事・育児と仕事のつらさ」のイメージがどうなっているのか見てみましょう。
【データで見る】男性の家事・育児参加の現状
男性の家事・育児参加時間は年々増加しているが、女性と比べると依然として大きな差がある
男女共同参画白書によると、
- 男性の「家事・育児・介護時間」は、女性と比べると圧倒的に少ない。
- 共働き世帯で、女性が就業している場合でも、男性の「家事・育児・介護時間」はわずかに増えているが、女性と比べると低水準。
- 6歳未満の子どもを持つ家庭では、女性の就業状態に関係なく、約7割の男性が何かしらの家事・育児をあまり行っていない。
データで見ると、男性の育児参加はまだまだ満足できる水準には達していないのが分かります。
- 男性の家事・育児の時間は増加傾向だが、女性に比べると以前として大きな差がある
- やっている”つもり”でも、実際には女性の負担が圧倒的に大きい
とはいえ、この”データ上の差”だけでは、育児と仕事の大変さを比べきれません。
次に、仕事と育児の負担の差について、実際の数字を見てみましょう。
【数字で比較】仕事と育児の負担の差
就業状態にかかわらず、女性の方が「家事・育児時間」の割合が多い
男女共同参画白書によると、
- 6歳未満の子を持つ男性の家事・育児関連時間は、平均で83分。一方で、女性は1日7時間34分との結果がある。
- 共働き世帯においても、女性の家事・育児時間は男性のおよそ2倍以上にのぼる。
- 男性の「仕事等時間」は、20代・50代は「7時間30分~8時間前後」、30代・40代は「8時間20分前後」に推移している。
数字を見れば人目で分かるように、
男性の育児時間は伸びているとはいえ、まだまだ女性の負担が大きいのが現状です。
- 育児と家事の負担は、女性に偏っている
- 女性がフルタイムで働いていても、家事・育児関連時間の割合は大きく縮まらない
それでは、世間の人たちは「どちらが大変」だと感じているのでしょうか。
「仕事と育児、どちらが大変?」世間の声は?
男性の中には、「仕事」より「育児」の方が大変だと感じている人もいる
「仕事と育児、どちらが大変なの?」
世間一般の考え方としては、次のとおりです。
<対象者>
0~12歳の子どもを育てている男女各50人
<結果>
「仕事の方が大変」と答えた人は、男性35%、女性15%。
「育児の方が大変」と答えた人は、男性65%、女性85%。
男性は、女性に比べて「仕事の方が大変」だと感じていますが、
”男女どちらとも、仕事よりも育児の方が大変だと感じている人が多い”という結果が出ています。
つまり、統計と世間の声をあわせると、
と言えます。
では次に、実際に育休を取得した私のリアルな体験談について説明していきます。
育休期間中のリアル談
育休を取得することで、”育児と家事の両立”がいかに大変なのか実感できた
実際に育休を体験してみて、
育児・家事がどれほど過酷で”終わりのないもの”なのかを痛感しました。
- 家事・育児には終わりがない
- 妻の心身への負担が大きい
- 夫婦で協力しなければ、とても家庭は回らない
この3つは、実際に育休を体験してみて初めて実感できた”リアルな大変さ”です。
日常的な家事をこなしている間にも、赤ちゃんの夜泣きの対応やオムツ替え、ミルクづくりなど、小さなタスクがたくさんあります。
そして、そのタスクは疲労とともに日々積み重なっていくのです。
🔗「育休期間って、実際はどんな感じなの?」
育休を取得することはできませんでしたが、1ヶ月間の”有給を取得して”感じたリアルな体験談をまとめた記事はコチラ👇️
【関連記事:育休は大変?パパが語る1ヶ月の育児休暇体験談 | 子育ての道しるべ】
仕事復帰後に見えた、『仕事と育児との大変さの違い』とは?
育休で家庭の現実を体験したからこそ、仕事に戻ってみて改めて見えた”育児と仕事の違い”がありました。
復帰後に直面したのは、数字では語れない”リアルな壁”だったのです。
この章では、仕事と育児との大変さの違いについて3つ紹介します。
仕事は休憩があるが、育児は休憩がない
仕事は休憩する時間があるが、育児は24時間無休です
育児中は、自分の好きな時間を確保することがほとんどできません。
ゆっくりと休むことはできず、ひたすら”終わりのない作業”を続けていきます。
一方で、仕事は自分のペースで休憩を挟むことができます。
休憩時間に何をやっても自由です。
娯楽を楽しんだり、ゆっくりご飯を食べたりなど、自由な時間を過ごすことができるのです。
-150x150.jpg)
でも、赤ちゃんが寝ているときは休めるんじゃないの?
赤ちゃんが寝ているときも、必ず家事があります。
哺乳瓶や衣類の洗濯、部屋の掃除、ご飯の準備など――
家事は山積みになっていくのです。
そして、ようやく片付けたと思ったら、また赤ちゃんに呼ばれてしまう。
この繰り返しです。
「いつ起きるかわからない」というプレッシャーも常にあるため、身体を休ませることは難しいのです。
仕事は成果が見えるが、育児は成果が曖昧で見えない
仕事と家事・育児では、目指しているところが全く違う
仕事は、努力した分だけ数字や評価で成果に現れます。
成果に繋がれば”やりがい”を感じますが、
育児は成果が目に見えにくく、終わりがないため、”やりがい”を感じる場面が少ないのです。
-150x150.jpg)
可愛さがあれば乗り切れるんじゃないの?
頻回に泣いている赤ちゃんの姿を見ると、「泣き止んだ」という安堵感よりも、次第に「また泣いてしまった」という焦燥感が強くなります。
一生懸命赤ちゃんと向き合っていても、”可愛さ”だけで解決できる問題ばかりではありません。うまくいかない場面もたくさんあるため、精神的にエネルギーを消耗してしまうのです。
🔖仕事復帰後は、”妻への後ろめたさ”がつらかった
育休が終ってからの生活は、どうしてもママに負担をかける時間が増えてしまいます。
育児の過酷さを経験したからこそ、ほとんどの家事・育児を妻に任せてしまうことに、モヤモヤした後ろめたさを感じていました。
仕事から帰宅して、寝室を覗くと、妻が泣いていたこともあります。
その姿を見たとき、胸が締めつけられるように痛くなり、「自分はもっと妻を支えられるはずなのに」と強く思いました。
そして、
限られた時間でも”できることを探して動こう”
と意識するきっかけにもなりました。
モヤモヤする後ろめたさを、そのまま罪悪感で終わらせず、行動のエネルギーに変えていくことが大切だと実感できたのです。
仕事は会話ができるが、育児ではきちんとした会話ができない
人と会話ができない状況下で生活することは、想像以上のストレスになる
仕事は「大人同士のやり取り」ですので、言葉が通じるし理屈や段取りで解決できる部分が多いです。
でも、育児ではうまくコミュニケーションが取れない時間が長く続きます。
赤ちゃんの言葉が分かれば解決できるものの、0歳~3歳頃までは言葉のキャッチボールができません。
「何を求められているのか分からない」
「話しかけても答えが返ってこない」
この環境下で生活することは、想像以上に過酷なものになります。
-150x150.jpg)
言葉が通じないって、そこまで大変なの?
『24時間独り言を呟きながら、気を張り続けた生活を送る状況』を想像してみてください。
とくに、女性は会話することで気持ちのリフレッシュができますので、会話が出来ない環境は、相当な精神的ストレスとなってしまうのです。
大変さとは、精神的な「質」の違いだった。
仕事と育児はどちらも大変だが、「精神的な疲労の質」がまったく異なる
仕事は「責任や成果」が重くのしかかり、育児は「終わりのないケア」が続くという性質があります。
ここではまず、仕事と育児がもたらす精神的な疲労について整理してみましょう。
仕事は、「責任の重さ」が疲労を生む
「仕事が大変」なのは、自分の行動や成果に責任がともなうから
仕事は、利益をあげることを目的に進められます。
計画を立てて行動し、ときには役割を分担してゴールを目指します。
残業があったとしても、必ず終業時間があり「一日の区切り」があるのも特徴です。
たとえば、仕事で生じる負担は次の通りです。
- 自分の行動や発言に責任がともなう精神的なプレッシャー
- 上司や同僚との人間関係のストレス
- ノルマや営業活動による体力的な負担
- 残務整理・残業といった時間的な圧迫
つまり、会社で働く限り、どんな行動にも何らかの負担はついて回るのです。
でも、仕事には逃げ場があります。
今の仕事が大変だと思うのであれば、転職して環境を変えてみる。
異動や働き方を見直してみるなど、自分の行動によって精神的・身体的な負担を軽くすることが十分に可能なのです。
この点が、育児との大きな違いとなります。
育児は、「分からなさ・終わらなさ」が疲労を生む
「育児が大変」なのは、ずっと終わりのないケアが続くから
育児は、親が行動しないと成り立ちません。
そして、親が行動しても解決できないこともたくさんあります。
たとえば、
- 泣き止んだと思ったら、数時間後にはまた泣き始める。
- 部屋をきちんと片づけたとしても、また散らかる。
- ご飯を作って食べさせても、数時間後にはまたお腹が空く。
などが挙げられます。
つまり、育児は”終わりがない”のです。
具体的な「ゴール」がなく、逃げ場もありません。
『明日やろう』という先送りも効かず、毎日「なぜ?」の繰り返しです。
常に気の抜けない状態が続き、睡眠不足にもなって気力・体力が無くなっていきます。
対価が発生するわけでもなく、社会的評価も得にくい状況がずっと続いていくため、精神的・身体的負担は蓄積していくばかりです。
- 仕事には区切りがあるが、育児には区切りがない
- 仕事には逃げ場があるが、育児には逃げ場がない
「仕事と育児、どちらが大変か」と比べることを止めよう
比べるのではなく、両者を尊重し合うことが大切になる
仕事と育児の”どちらが大変か”を比べることに意味はありません。
なぜなら、仕事も育児も大変であって、大変さの”質”がまったく異なるからです。
「仕事で疲れているから」と言うよりも「お疲れ様」と言えるように、育児・家事に対する考え方を変えましょう。
そして、やはり一番の有効な手段は育休を取得することだと思います。
赤ちゃんと向き合い続ける環境が、いかに過酷な状況なのかを実感できるからです。
-150x150.png)
正直なところ、私は育児の方が大変だと感じました。
なので、育休後も”大変さ”を比べることはせずに、”大変さの種類が違う”と理解して行動するようにしました。
仕事で疲れていたとしても
限られた時間で、どのように家族と向き合うのか――
きちんと考えて行動しましょう。
- 夫婦で、お互いに”大変さの質が違う”と理解して尊重し合うことが大切になる
まとめ
パパは”仕事をしてるから偉い”ではなく、家庭でも役割を果たしましょう。
”自分にできること”を探して実行する。
「どちらが大変か」ではなく「どう協力するか」を夫婦で考えて行動していく――
そうすることで、パパもママも「大変さを認め合える関係」になり、結果的に仕事と育児との両方で、心のバランスが取りやすくなります。
パパが動けば、ママも子どもも、もっと笑顔になれます。
完璧じゃなくても大丈夫です。
今日から、できることを一つでも行動に移してみましょう。
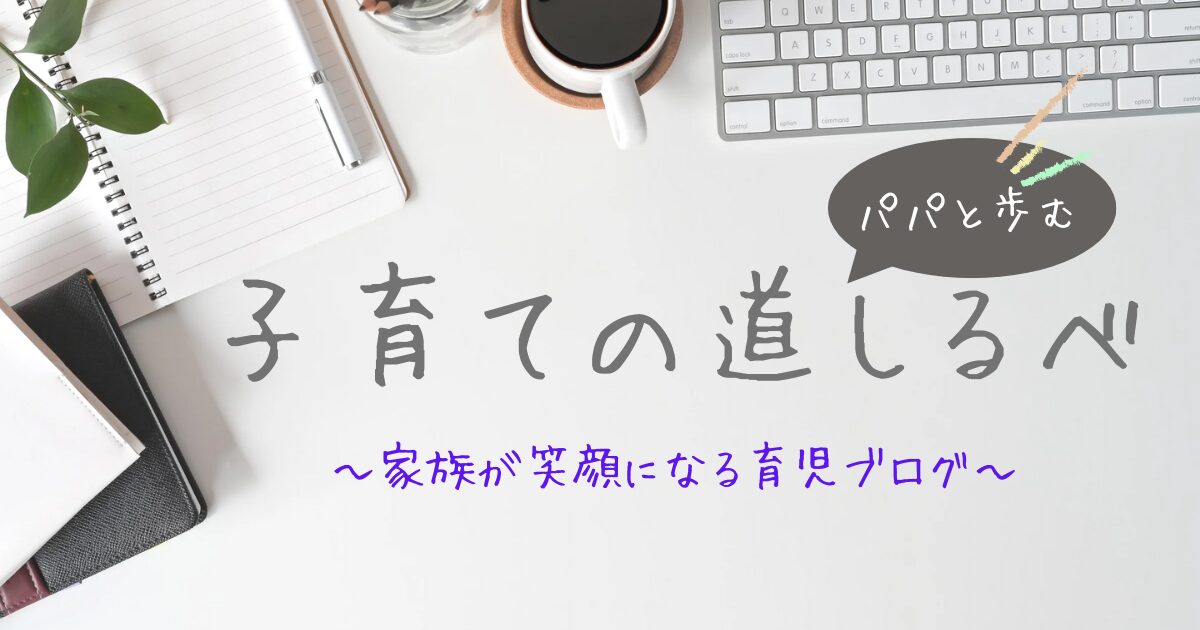


-120x68.png)
コメント