「育児休暇」と聞くと、赤ちゃんとゆっくり過ごせる特別な時間をイメージする方もいるかもしれません。
でも、実際に育休を取ってみるとその印象は大きく覆されました。
次々に押し寄せる”初めての経験”に圧倒されて、想像以上に過酷な日々。
決して「楽な時間」ではなかったのです。
それでも私は、育休を取って本当によかったと心から思います。
ママと一緒に学びながら赤ちゃんと向き合う中で、楽しい瞬間・嬉しい瞬間もたくさんありました。
そして「家族を大切にしよう」という気持ちが、確実に強くなったのです。
この記事では、パパ目線で実際に体験した「育休のリアル」をお伝えします。
これから育休を考えている方にとって、少しでも役立つヒントになれば嬉しいです。
🖊️この記事でわかること
はじめに
私は第一子の誕生を機に、育児に専念するため休暇を取得しました。
周りの男性で休暇を取る人はおらず、正直なところ不安も大きかったです。
でも、取得を決めた理由はシンプルでした。
「妻と一緒に育児をしたい。赤ちゃんの成長を一番近くで見守りたい」という気持ちです。
実際に育休を過ごしてみると、想像以上に大変なことの連続でしたが、同時に家族の絆が深まる大切な時間でもありました。
この記事では、育児休暇に向けた事前の準備や、育休期間中にパパが初めて挑戦した育児の実体験談について紹介していきます。
育児休暇は早めに申請しよう
育児休暇の申請は、最低でも1ヶ月前に上司へ相談しよう
育児休暇を取得する時は、仕事の引き継ぎを含めて迅速に相談をすることが望ましいです。
そして、大切なのは「何ヶ月取るか」よりも、どのようにその期間を過ごすか。
なぜなら、育休の過ごし方ひとつで家庭の雰囲気は大きく変わってしまうからです。
- どのように子どもと向き合うか
- ママにどんなサポートができるか
意識して、心の準備と生活のシミュレーションをしておきましょう。
🔗「育休が取れなくても、家族のそばにいられる方法はあります」
私は、育休ではなく有給を取得して家族と向き合う時間を作りました。有給を取得して過ごした1ヶ月間についての実体験をまとめた記事はコチラ👇️
【関連記事:育休は取れなかった。でも”1ヶ月の有給”が教えてくれた家族のかたち | 子育ての道しるべ】
ママが入院中にやるべきこと
育休は「赤ちゃんとママが退院してから」ではありません。
入院中からすでに始まっているのです。
この章では、ママが入院している間にパパがやるべき準備について紹介します。
部屋の整理整頓をしよう
赤ちゃんが安心して暮らせる環境をつくるために、整理整頓は必須です。
たとえば、
などが挙げられます。
部屋が散らかっていると、その分転倒するリスクが増えてしまいます。
でも、整理整頓を心掛けていれば、最初から事故を防ぐことができるのです。
育休の初めに環境を整えておくと、その後の生活がぐっと楽になりますので、部屋の整理整頓は行いましょう。
育児に必要なものを買い揃えよう
育休が始まると、買い物に出かけるのも大変になります。
最低でも1ヶ月分の育児用品は事前に揃えておきましょう。
事前に揃えておきたい育児用品としては、
| 用品名 | 内容 | 補足(ポイント) |
|---|---|---|
| おむつ | 新生児サイズ | 1日8枚以上使用します |
| おしりふき | 大容量のもの | 肌に優しいタイプ推奨です 1箱あれば十分です |
| 紙おむつ処理袋 | 大容量のもの | 1日3袋前後使用します |
| ガーゼハンカチ、 タオルケット | 各7~10枚 | 吐き戻し・汗ふき、沐浴のときに大活躍します |
| ベビーソープ、 保湿ローション | 各1本 | 詰め替え用も準備しましょう |
| 着替え | 肌着・ロンパースなど | 最低でも1日2回以上、着替えをします |
| 粉ミルク | 医師や看護師に勧められたもの、またはママが入院中に使っていたもの | 1日8回以上、ミルクを飲みます |
| 哺乳瓶、乳首 | 新生児サイズ | 哺乳瓶は1~2本、乳首は2個前後が推奨です |
このような用品が必要になってきます。
-150x150.png)
入院前に準備するものもありますので、どれをどのくらい揃えるかは、ママと相談しながら一緒に決めておきましょう。
🔖事前に準備しておきたい持ち物リストをまとめました✨️
【育休パパの赤ちゃんグッズ準備チェックリスト(PDF)】
パパ一人でも買い物がしやすいようなチェックリストになっていますので、ぜひ活用してみてくださいね✨️
最初の”初めて”に備えよう
退院日は、出産を頑張ったママと赤ちゃんとの感動の対面です。
ですが、その直後からパパは数々の”初めて”に直面します。
- ”初めての抱っこ”
- ”初めてのチャイルドシート移乗”
- ”初めての赤ちゃんを乗せた運転”
これらは退院当日に一気にやってくるのです。
パパは必ず「抱っこ」と「チャイルドシートへの移乗方法」だけでも必ず予習しておきましょう。また、他にもミルクの与え方や沐浴の仕方、おむつの替え方などについても予習して心の準備をしておきましょう。
-150x150.png)
抱っこに不慣れなまま、チャイルドシートに乗せようとした時のこと。
「赤ちゃんをしっかり支えなきゃ!」と緊張するあまり、手が震えていたのを覚えています。
チャイルドシートに乗せる動作は想像以上に難しいので、退院前に何度か練習しておくと安心ですよ。
- 赤ちゃんと一緒に過ごす部屋”だけ”でも、整理整頓をしよう!
- 育児に必要なものを買い揃えよう!
- 育児本や動画を見て、育児の予習・復習をしよう!
次の章からは、どのような育児休暇を過ごしたのかについて振り返ります。
育児休暇1ヶ月の前半|想像以上に大変だった最初の2週間
育休が始まってすぐの生活は、とにかく不安と緊張感でいっぱいだった
目の前にいるのは、可愛くて、か弱い赤ちゃん――
ぐっすり眠っていても「ちゃんと呼吸しているかな?」と胸の上下を確認する毎日。
些細な物音やうめき声にも体が瞬時に反応し、終日気を張り続けていました。
さらに、出産直後のママの体はまだ回復途中。
サポートが欠かせない中で「自分も疲れているけれど、ママのケアも赤ちゃんのお世話も両方やらなければいけない」というプレッシャーが常にありました。
そして、そんなプレッシャーの中、さらに精神的に追い込むように赤ちゃんが泣いて「ママ」「パパ」と訴えてくるのです。
赤ちゃんが泣き止まないときの不安と向き合う方法
赤ちゃんは1~2時間ごとに泣いたり泣き止んだりを繰り返します。
「なぜ、泣いているのだろう」
最初は、すべてが手探り状態でした。
ミルクやオムツ交換で泣き止むこともありますが、何もしても泣き止まないこともありました。
泣き止んでせっかく眠ったと思っても、ちょっとした刺激ですぐに目を覚ましてしまうなんてことも…。
- 抱っこしてもダメ
- オムツや服を替えてもダメ
- 室温を調整してもダメ
このように「どうしても泣き止まない状況」が必ず訪れます。
原因が分からないことも多いからこそ、ママに任せるのではなく、パパ自身が「自分がやらなきゃ!」と責任感を持って、率先して向き合いましょう。
-150x150.png)
ウチの子は、育休を終えた数ヶ月後、どうしても泣き止まない時期がありました。でも、その時に慌てずにあやすことができたのは、育休中に”泣き声と向き合う経験”を積んでいたからだと思っています。
📌どうしても泣き止まないときこそ、パパの出番!
前述のとおり、どうしても赤ちゃんが泣き止まない場面が必ず訪れます。
そんな時こそ、ママとバトンタッチしましょう。
赤ちゃんを抱っこしながら優しく語りかけ、平らな場所を淡々と歩き続ける。
眠ったように見えても、すぐにベッドへ置かず、しばらく抱っこを続けて”深い眠り”を確認してから寝かせてみるなど――
泣き止まない夜を乗り切るコツは、パパにあります。
-150x150.png)
毎日泣き声を聞き続けていると、次第に「また泣いたらどうしよう」と不安になり、我が子の泣き声そのものが怖く感じてしまうことがありました。
「可愛くて仕方ないはずの存在なのに、恐怖の対象になってしまった」――
これが正直な気持ちです。
それでも、必死に向き合い続けたからこそ、次第に「泣いても大丈夫」と思える余裕を持てるようになりました。
- ママに任せるのではなく、まずは自分でなんとかしてみよう!
- どうしても泣き止まないときこそ、パパが率先して抱っこしてみよう!
初めての育児体験|パパが直面する抱っこ・授乳・沐浴
赤ちゃんと過ごす育児休暇は、とにかく”初めて”の連続。
特に、パパにとっては「初めての抱っこ」「初めての授乳(ミルク)やげっぷ」「初めての沐浴やおむつ替え」などが大きな関門になります。
育児本や動画で知識を得ていても、実際にやってみると「泣き止まない」「げっぷが出ない」「沐浴中に手が震える」など、想像以上に難しく感じることがあります。
ここでは、私が育休中に体験した”初めての育児”について、リアルなエピソードと一緒に紹介していきます。
パパが初めて挑戦する抱っこ・寝かしつけ
赤ちゃんを抱っこするのは、新米パパにとって最初の大きな試練です。
育児本や動画では「こう抱けば安心する」「泣き止む方法」と紹介されていますが、実際に抱っこしてみると全然泣き止まないことが多々ありました。
頭や首をしっかり支えながら抱いても泣き続けてしまう…。
最初は「自分の抱き方が悪いのかな?」と不安になるばかりでした。
でも、大切なのは安全に抱っこすること。
他にも、
- リズムよく歩きながら背中をトントンしてみる
- 抱っこの姿勢を変えてみる
- 泣き止まなくても「今は泣いても仕方ない」と割り切る
など、繰り返しトライしてみましょう。
次第に、赤ちゃんが落ち着く抱き方やリズムのコツが少しずつ分かってきます。
-150x150.png)
「落ちないように」「自分の体に寄せるように」と意識するだけで安心感が出ました。泣き続けていても、毎日赤ちゃんと向き合ううちに「泣いても大丈夫、必ず落ち着くときが来る」と思えるようになりますよ。
寝かしつけも同じです。
赤ちゃんを抱っこして背中を優しくトントンしたり、添い寝で安心させたりなど。
「これなら落ち着く」というルーティンを見つけましょう。
- 毎晩同じ時間に、暗くして静かな環境をつくろう
- 寝る前に、授乳したり絵本を読んだりなど、”順序を統一した”習慣づくりをしよう
- 朝は自然光で明るくして、赤ちゃんの体内時計を整えよう
▶それでも眠ってくれないときは、やっぱり抱っこが一番です。
パパが初めて挑戦する授乳(ミルク)・げっぷ
授乳はシンプルに見えて、実際はかなり難しいものです。
「温度が熱すぎる」「飲むのが速すぎてむせる」「途中で嫌がる」など――
想定外のことが次々に起こるからです。
特に大変なのは、夜中の授乳です。
眠い中でお湯を沸かし、ミルク粉を計量し、適温に冷ましてから哺乳瓶を口にあてる。
やっと飲んでくれたと思ったら、数十分後にまた泣くこともあります。
疲労感と睡魔と戦いながら、授乳の準備を整えることは想像以上に大変なのです。
-150x150.png)
どんなに疲れていても、一番気をつけたのは火傷です。
哺乳瓶は必ず温度を確かめてから飲ませました。赤ちゃんが吸ってくれない時は、口の奥に少し哺乳瓶の口を押し進めてあげると吸い始めてくれますよ。
- 水をポッドに入れて沸騰させる
- 沸騰した水をコップに入れて、ラップした状態で冷蔵庫に冷やしておく
- 必要なミルク粉を哺乳瓶に入れて、沸騰した70℃以上のお湯で溶かす
- ②で準備した”湯冷まし”を、③に加えて必要量に整える
▶最初の頃は、熱い哺乳瓶を冷やして適温に調整していましたが、この方法に変えてからぐっと時間短縮になりました。
そして、授乳の後はげっぷに挑戦です。
これもまた難関でした。
育児本や動画では「縦抱きでトントン」「膝の上に座らせてさする」などとありますが、力加減が分からずに戸惑ってしまったのです。
「このやり方で、本当にげっぷが出るのかな」と不安にもなりましたが、
妻に力加減をレクチャーしてもらったり、何回も積極的に続けたことで次第に力加減が分かるようになりました。
-150x150.png)
私は人差し指と中指の2本でトントンしていました。叩く手は固定して指だけで動かすイメージです。最初にげっぷが出たときの力加減を覚えておくと、次からはぐっとやりやすくなります。
パパが初めて挑戦する沐浴・お着替え(おむつ替え)
沐浴(お風呂)も、新米パパにとって大きなハードルです。
赤ちゃんを沐浴させるまでの事前準備と、注意すべきことがたくさんあるからです。
たとえば、
- ベビーバスやベビーソープ、ガーゼハンカチ、洗面器、沐浴布、バスタオルなどを準備する
- お湯の温度を38~40℃を目安に調整する
- 沐浴前の赤ちゃんの体調を確認する
- 顔や頭が沈まないように片手でしっかり支える
- 顔の拭き方や体の洗い方、そして力加減を注意する
などが挙げられます。
特に「片手で頭を支えながら、もう片手で洗う」という動作は、慣れるまでかなり緊張しました。
-150x150.png)
片手で赤ちゃんの体を支えて、反対の手で洗う動作は本当に難しかったです。
慣れてきても疲労が溜まると手元が危うくなるので、常に「赤ちゃんの頭は重たい」と意識していました。最初のうちは、二人で協力して役割を分担することが特におすすめです。慣れてきたら一人で挑戦してみましょう!
沐浴後は、着替えとおむつ替えです。
「小さな体をどう扱えばいいのか」と大変戸惑いました。
でも、大切なのは焦らずゆっくり丁寧に進めること。
「泣いているから早くしなきゃ!」と慌てるよりも、優しく声をかけながら進めたほうがパパも赤ちゃんも安心できます。
育児本や動画で「正しいやり方」を学ぶのも大切ですが、実際は赤ちゃん一人ひとりに合った方法を探すことがもっと大切です。
失敗や戸惑いの連続ですが、「抱っこのコツ」「寝かしつけの工夫」「授乳(ミルク)や沐浴のポイント」を実体験から学んでいくことで、家族の安心とパパの自信にも繋がります。
育児休暇1ヶ月の後半|心身ともに限界な日々
半月が過ぎると、心身への疲労は一気に押し寄せてきます。
寝不足による倦怠感、血圧の上昇、集中力の低下など――
体の不調が重なると、生活の質そのものが落ちてしまうのを実感しました。
自分たちの食器洗いや洗濯は後回し。
ときにはシャワーすら浴びず、そのまま眠りに落ちることもありました。
それでも、赤ちゃんの世話だけは最優先です。
衣類やガーゼ、タオル類の洗濯は最低でも1日2回。哺乳瓶の洗浄や消毒も欠かせません。
育休は「体力勝負」になります。
育休を長く取得したいと考えている場合は、あらかじめ「無理をしないペース配分」を意識しておきましょう。
この章では、疲れがピークに達したときに注意したいこと、疲れた中でどのように育児と向き合っていったのかについて、実体験談を紹介していきます。
疲れがピークになったときこそ注意したい3つの意識
疲れているときほど、ちょっとした気の緩みが大きな事故につながる可能性があります。
特に、私が意識していたのは次の3点です。
- ”抱っこでは絶対に落とさない”意識を!
どんなに眠くても、赤ちゃんを「自分の体に寄せるように抱くこと」を徹底しました。
抱っこして座ったまま寝落ちしてしまったこともありましたが、必ず手は添えていました。 - ミルクは温度チェックを慎重に!
眠いとつい確認を怠りがちですが、熱すぎても冷たすぎても赤ちゃんには負担になります。哺乳瓶を必ず自分の手首にあてて、適温を確認する習慣をつけていました。 - 沐浴ではお湯の事故を防ぐ!
疲労で手が滑ると、口や鼻にお湯が入ってしまう危険があります。
「赤ちゃんの頭は重たい」と心の中で繰り返しながら、注意して支えていました。
-150x150.png)
育児は「疲れていても絶対にやらなければならない場面」が多いです。
そんなときこそ「自分なりの安全ルール」を持っておくと安心ですよ。
育児休暇中こそ、赤ちゃんの成長記録を残そう
育休中にぜひ取り入れてほしいのが、赤ちゃんの成長記録を残すことです。
赤ちゃんの生活リズムや体調の変化を「見える化」したことで、とても大きな助けとなりました。
成長記録をつけるメリット
- 行動バターンが分かる!
授乳やおむつ替えの時間を振り返ることで、泣く理由を推測しやすくなる。 - 体調の変化に気づきやすく、育児の安心感につながる!
検診や病院で「いつから症状があるか」を正確に伝えやすくなる。 - 夫婦で共有できる!
どちらが担当しても、記録を見れば状況をすぐに把握できる。
記録の方法
- ノート派
夫婦で1冊を共有すれば、思い出として残せるアルバムにもなる。 - アプリ派
授乳やおむつの記録を入力でき、グラフ化してくれる機能もある。
🔖余談
ウチでは、妻が入院中からノートに記録をつけ始めました。
「ミルクをどのくらい飲んだか」「おむつ替えの時間」「排泄の有無」「身長や体重の記録」などを毎日書き続け、1歳を過ぎるまで記録に残していたのです。
-150x150.png)
育休期間が終わった後も、妻は毎日記録を続けていました。そういう姿を見ているからこそ、パパとして「もっと頑張らなきゃ!」と気持ちを新たにすることもできました。
おすすめは、ノートで成長記録を残すこと
育児に少し余裕が出てから当時の成長記録ノートを見返すと、
「あのとき、夜中はこんなに起きていたんだ」
「この時期に初めて笑ってくれたんだ」
「身長がこんなに伸びていたんだ」
といった、思い出アルバムにもなります。
とても大変な時期だけれど、その瞬間の頑張りが、後になって家族の宝物になります。
そんな意味でも、ノートで成長記録を残すことはおすすめです。
ご両親・義父母の協力を得よう!
初めての育児では、親世代の存在が大きな支えになります。
「上手くいかないこと」や「自分たちだけでは解決できないこと」は、遠慮せず相談しましょう。
-150x150.png)
泣き止まない時の対処法について両親に相談したことがあります。
『◯◯が子どもの頃はこうだったよ』というアドバイスも、意外と役に立ちました。「他にもなにかできることないかな?」と言われたときは、とても嬉しかったです。
頼ることに罪悪感を持たず、「協力してもらうのも育児の一部」と割り切ることが、心身の負担を軽くしてくれます。
育児休暇を終えて
休暇期間終が終わっても、育児が終わるわけではありません。
むしろ「これからが本番」と言えるでしょう。
育休中と育休終了後の生活リズムを比べると、その差は歴然です。
| 時期 | 家事・育児の時間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 育児休暇中 | 24時間ずっと家事・育児 | 赤ちゃんとママを中心にした生活。日常のほとんどが育児で埋まる |
| 育児休暇終了後 | 仕事終わりから3〜5時間程度 | 残りの洗濯や食器の片付け、部屋の整理整頓など。限られた時間でこなす必要あり |
つまり、家族と向き合える時間は圧倒的に減るのです。
たとえば、
- 洗濯物をたたむ
- 食器を片付ける
- 部屋を整える
- 翌日の準備(哺乳瓶・ミルク・オムツ補充)
- 寝かしつけ
など、1日3~5時間でやれることはどうしても限られてしまいます。
なので、育休を終えた後は、特に”これ以上ママの負担を増やさないように”と意識して行動しましょう。
-150x150.png)
育休を終えた後も、私は夜熟睡することはありませんでした。というより、「できなかった」のです。どこかで、妻に対して後ろめたい気持ちを抱えていたから。「夜だけでも私の番!」と意識して気を張り続けていました。
仕事ももちろん大切です。
でも、仕事の疲労と育児の疲労はまったく別物です。
「限られた時間で、自分ができることは何か」考えて行動しましょう。
- 育休が終わっても、ママは変わらず育児に時間を注いでいることを忘れないこと
- 仕事は仕事、育児は育児と切り分けて”自分の役割”を意識しよう
🔗「仕事と育児、どっちが大変なの?」
私の体験談を交えて、仕事と育児との大変さの違いについてまとめた記事はコチラ👇️
【関連記事:【パパ必見】仕事と育児どっちが大変?リアル体験から見えた”本当の違い” | 子育ての道しるべ】
おわりに
育休は、決して楽な時間ではありません。
慣れない育児、寝不足、家事との両立など、思っていた以上に大変な毎日でした。
それでも、その「大変さ」を家族と一緒に乗り越えたことで、夫婦の絆や子どもへの愛情もぐっと強くなりました。
だからこそ、これからパパになる人には、ぜひ勇気を出して一歩踏み出してほしいと思います。
育休は挑戦の連続ですが、振り返れば「大変だったけど、本当に取ってよかった」と心から思える時間になるはずです。
同じパパとして、あなたの挑戦を応援しています。
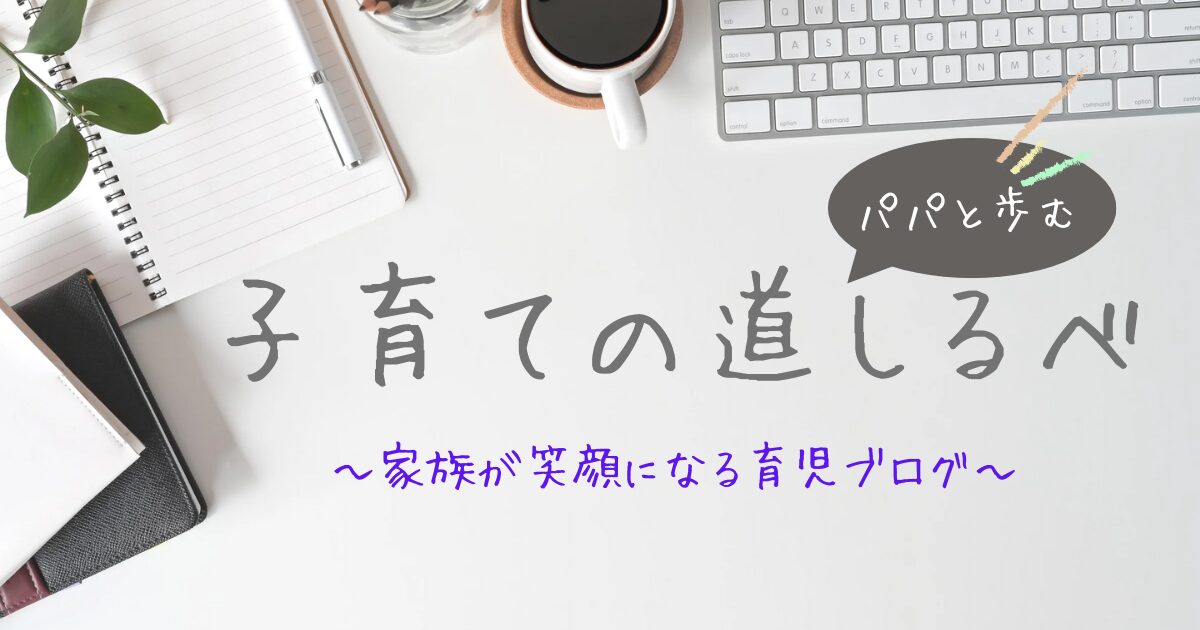
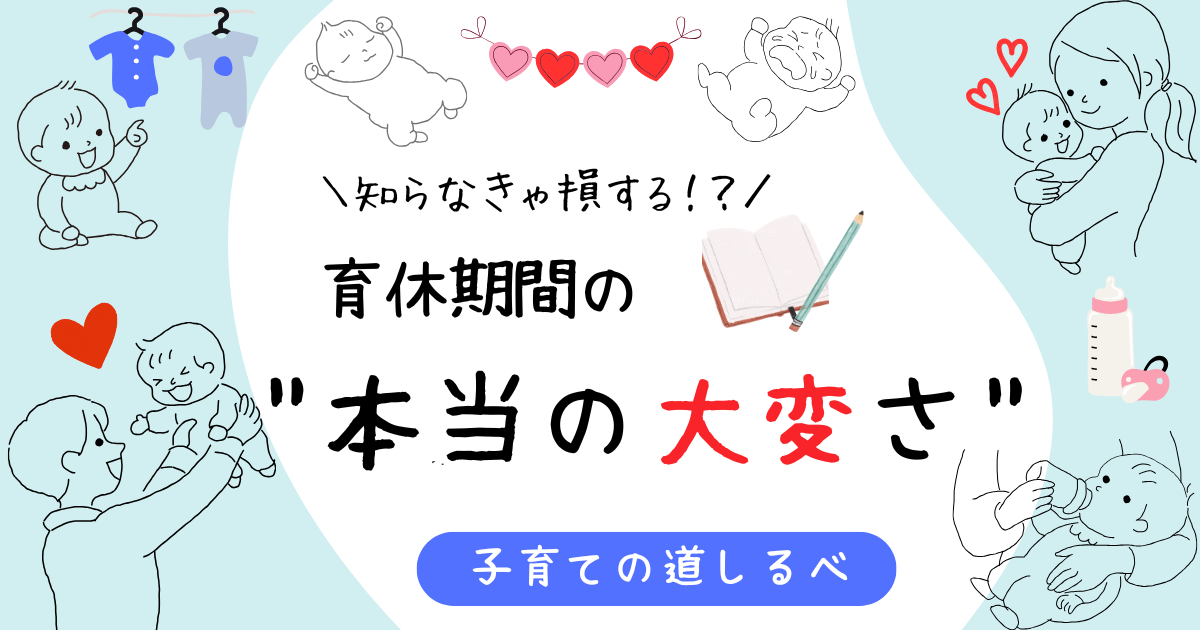


コメント