※本記事は、私たち家族の体験談をもとにした内容です。
専門的な診断・治療を目的としたものではなく、あくまで「私たちがどう対応したか」の記録です。ご心配な症状がある場合は、必ず医療機関や相談窓口にご相談ください。
「け、けいれん!?」
妻は明らかに動揺していました。
初めて子どもが熱性けいれんを起こした、あの日。
息をしているのかも分からないまま、ただただ抱きしめることしかできませんでした。
今でも、あの時の記憶は消えません。
熱が出るたびに「またけいれんが起きてしまうのでは?」と胸がどきどきしてきます。
この記事は、
- 同じような経験をしたママとパパ
- 「うちの子もなるかもしれない」と不安なママとパパ
へ向けて、
- 我が子が経験したリアルな様子
- 私たちがとった行動
- 親として、どんな「心構え」をしておけばいいのか
について、少しでも心の準備や安心を届けたくて書いています。
熱性けいれんを体験して伝えたいこと
私が伝えたいことは、一つだけです。
それは、
一人より、二人で看病してほしい
ということ。
子どもが熱を出したとき、つい「ママに任せっぱなし」になっているパパいませんか?
たとえ熱だとしても、ママは怖くてたまらないのです。
もう一人がいるだけで、ママは安心できます。
パパは「子どもが元気でいることが、当たり前じゃない」という気持ちを、どうか忘れないでいてほしい。
二人で支え合って、乗り越えていくものだということを心にとめて、
今日も夫婦ふたりで育児に励んでくれたらと切に願っています。
熱性けいれんとは?
熱性けいれんとは、
38℃以上の発熱時に起こるけいれん(ひきつけ)発作のことです。
生後6ヶ月~5歳くらいまでの乳幼児に多く見られます。
この現象は、成長とともにほとんどが自然に消失し、6歳頃にはほとんど発症しなくなります。
また、両親や兄弟姉妹に熱性けいれんの既往がある場合、発症リスクが高まるとされています。
熱性けいれんの典型的な症状例
症状としては、
など、があげられます。
これらの症状がすべて出るわけではありませんが、一つでも当てはまった場合には落ち着いて対応することが望まれます。
熱性けいれん時の適切な対処例
我が家では、事前に熱性けいれんが起きたときに対応方法を共有していました。
例えば、
我が家が事前に「熱性けいれん」について参考にしていた記事はコチラです👇️
体験談①|初めてけいれんが起きた日|私たちはどう動いたか
初めて子どもが熱性けいれんを発症したとき、
事前に学んでいた知識はすべて真っ白になってしまいました。
この章では、実際に熱性けいれんを経験したあの日について振り返っていきます。
- 発症の瞬間
- 子どもの状態や親の心境
- どのような対応をしたのか
について、リアルな体験談を紹介します。
熱性けいれん発症の瞬間
その瞬間は、突然やってきました。
38℃以上の熱が続いていた、ある日。
子どもは少しぐったりはしていましたが、重篤な様子ではありませんでした。
食欲はやや落ちていましたが、水分も摂れ、おもちゃで遊んだりテレビを見たりして過ごしていました。
その日、私は午前中で仕事を終えて、お昼に帰宅。
帰宅すると、子どもはママの膝の上で横になって休んでいました。
「ただいま」
「大丈夫?」
と聞くと、子どもはニコッと笑ってくれました。
子どもが次第にウトウトし始めたため、家族3人で横になりお昼寝の準備を開始。
子どもが眠ったことを確認し、
妻と私も一休みしようとした瞬間――
突然、体がガクガクと震え始めたのです。
ママは動揺する中、パパは理性を保とうとした
「けいれん!?」
妻が大声で慌て始めました。
ピクピクなんてかわいらしい震えではない。ガクガクと大きく震えていたのです。
私はというと、
「落ち着かないと!!」
と必至に理性を保とうとしました。
子どもの顔はみるみるこわばり始め、口からは泡も吹き出していく。
この小さいからだの中で、「何が起きたか分からない」恐怖を感じました。
「救急車を呼ぶべきか……」
悩んでいる時間すら無く、ただただ子どもに声をかけていました。
「大丈夫!」
「大丈夫!」
「◯◯は強い子だよ!」
懸命に何度も話しかけましたが、
きっとそれは、自分自身を落ち着かせていただけかもしれません。
短くて長いけいれん。
でも、実際に目の前で起きると、
その「数分・数秒」が信じられないほど長く感じました。
次第にこわばりが無くなっていき、
体から力がスッと抜けていく――
そして、泣き始めた瞬間を見て、
「あぁ、生きてる」
「良かった」
と、心の底から安心しました。
救急車を呼ばず、かかりつけの病院へ
「意識がある。良かった」
子どもを抱っこして、「意識があるかどうか」何度も確認していました。
一方で、ママはかかりつけの病院へ連絡を開始。
状況を説明したあと、幸いにも診察の了承をいただいたため、病院へ出発しました。
待ち時間の間は、ずっと子どもを抱っこした状態。子どもは泣いていましたが、
生きている――
それだけで、私たちは安堵できたのです。
診察室から名前を呼ばれ、医師との問診が始まりました。
📍医師の問診・診察内容
※我が家で、実際の行った会話のやり取りを再現しています。診断や処方を保証するものではありません。

どのくらいの間、けいれんしていました?

だいたい、1分半くらいです。5分は経っていないと思います。

けいれんは、両手両足?
左右どちらもけいれんしてましたか?片方だけ(けいれんがあった)とかありませんでしたか?

はい、両手両足のどちらもけいれんしていました。

吐いたりとかはしていませんか?

はい、大丈夫でした。
他にも、胸の音を聴診したり手足の発赤の有無を確認したりなど、丁寧に診察していただきました。

けいれん止めの坐薬を出します。もし、夜38.5℃以上の熱が出た場合には挿肛してください。

分かりました。けいれんが無くても使っていいんですね?

大丈夫です。
病院からは、抗けいれん薬と解熱鎮痛剤の2種類を処方されました。
どちらも同時に使ってもよいことを確認して診察が終わりました。
処方された薬は、必ず医師の指示を受けて使用するようにしてください。
診察を終えた頃には、子どもは落ち着きを取り戻していました。
あまりにも長く感じた一日が終わった
病院から自宅へ戻ると、子どもは「パン、たべる」と一言。
あのときは、
「口に入るのであれば何でも良い」
「とにかく落ち着いてよかった」
という気持ちが強かったです。
そして――
「よく救急車を呼ばずに、様子を見ることができたな」
という強い不安感が後から押し寄せてきました。
また、妻からも
「一人じゃなくて良かった。あと、夜じゃなくてよかった」と一言。
でも、
「もし夜だったら?」
「もし一人だったら?」
そんな「もしも」が、今でも時々よぎります。
あの日の夜は、心配で心配で眠れませんでした。何かあってもすぐ対応できるようにと、ずっと神経を張りつめていた状態だったのです。
子どもの寝息を何度も確かめ、
- 体が熱くないか
- 顔色に変化はないか
- 震えていないか
など、ただひたすら見守っていました。
こうして、初めてのけいれんとの闘いは幕を下ろしたのです。
初めてのけいれんを振り返って
「頭が真っ白になる」
初めて経験したことでした。
ここでは、
- うまく対処できたこと
- 反省点と解決案
について振り返ってみます。
🔖うまく対処できたこと
- 冷静さをやや保つことができた
「どうにかしなきゃ」という気持ちが勝ったんだと思います。
でもたまたまそうなっただけかもしれません。 - けいれんが終わったあとも、子どもの様子を落ち着いて見れた
- 医師の指示通り処方薬を使えた
発症した夜0時半頃、子どもの熱が38.5℃に上がったため、処方薬を使用することができました。

薬を使うときも緊張が走りました。でも「できることはすべてやろう」という気持ちで対処できたため、ほんの少しだけ自信にも繋がりました。
🔖反省点と解決案
- けいれんの時間を計れなかった
けいれんが始まった瞬間、こどもから目を離すことができなかったため、時計を確認する余裕はありませんでした。
<解決案>
スマホを起動する余裕はないため、すぐ目の届く範囲にアナログの時計を置いておく。 - 顔を横に向けて寝かせることができなかった
つらそうな我が子の姿を見て、居ても立っても居られず、気づいたら抱きかかえてました。
<解決案>
熱が出た時は、顔を横に向けるように意識しよう。
体験談②|2度目のけいれんが起きた日|新たなハプニングが発生
初めてのけいれんから1年が経ち、子どもも熱を出さずに元気に過ごす時間が増えてきました。
でも、やはり1度目のけいれんのことは頭から離れません。
初めてけいれんしたあの日が近づくにつれて、「熱が出ませんように」と願うようになっていました。
そんな中、また2度目のけいれんが起きてしまったのです。
2度目の発症の瞬間
その日は、39℃を超える熱が続いていた中で、突然やってきました。
子どもの様子は、
- 食欲はなく、水分も摂りたがらない
- 横になっている時間が多い
- テレビやおもちゃに関心を向けない
など、1度目の発症のときよりも体調が悪い印象でした。
子どもと一緒にお昼寝をしようと、準備を開始。
家族3人で横になって子どもが眠ったことを確認。
私たちも一休みしようとした瞬間――
また、突然体がガクガクと震え始めたのです。
けいれんが止まっても反応が無かった
ガクガクと大きく震えている我が子。
顔はみるみるこわばり、口からは泡も吹き出している。
ここは1度目と同じですが、2度目のけいれん時は、
など、1度目のけいれん時とは明らかに様子が違っていたのです。
次第に体のこわばりが無くなっていき、力がスッと抜けていく。
「また泣き始めるのかな?」
そう思っていましたが、一向に泣き始めなかったのです。
――全身に力が入っていない。
1度目の時とは比べられないほどの絶望感が、押し寄せてきました。
大声で呼びかけ、手や足を握りしめ、何度も呼吸しているか確認しました。
そのとき、口が微かに動き、
私の指を、かすかな力で握ろうとした姿を見て、
「あぁ、生きてる」
と、また心の底から安心できたのです。
そして、そんな中あらたな問題が発生しました。
かかりつけの病院が休診だった
その日、かかりつけの病院が休診だったのです。
「かかりつけの病院に受診できない」という絶望感。
やむを得ず、近くの小児科や市の緊急診療所へ相談を始めました。
でも、
と、案内を受けたのです。
高熱、けいれん後で脱力している状態、意識もボーッとしている、反応が鈍い…
このような状態で、
「以前処方された薬を使ってもよいのか」
「救急車を呼んだ方がいいのか」
など、明らかに動揺していました。
苦肉の策ではありましたが、迷った末に職場の医師へ連絡することにしました。
状況を伝えると、「今すぐにでも坐薬を使用して良い」と医師から指示を受けたため、以前処方された2種類の坐薬を使用しました。
坐薬を使用したあとも、不安な気持ちは変わりません。
病院に連れて行けないことが、ここまで精神的に追い込んでくるとは想像していませんでした。
その日、子どもの顔を見ながら
ただただ、
「もう、2度とけいれんは起きないでほしい……」
と願わずにはいられませんでした。
翌日、かかりつけの病院へ
幸いなことに、けいれんは起きずに翌朝を迎えることができました。
朝一番でかかりつけ医を受診。
問診内容は1回目のときと大きくは変わりませんでした。
📍医師の問診・診察内容
※我が家で、実際の行った会話のやり取りを再現しています。診断や処方を保証するものではありません。

つらかったですね。
けいれんが止まっているのは良いことです。このまま熱が下がっていくといいですね。

ありがとうございます。
これからも高熱が出た際に、8時間空けていれば坐薬を使用してもいいでしょうか?

大丈夫ですよ。
お大事にして下さいね。
医師のその言葉に、ようやく少しだけ肩の力が抜けたのを覚えています。
当日も高熱が続いていたため、その場で再び坐薬を挿肛していただきました。
あらためて、病院から2種類の坐薬を処方してもらい帰路に着いたのです。
処方された薬は、必ず医師の指示を受けて使用するようにしてください。
2度目のけいれんを振り返って|1度目のけいれんとの比較
ここでは、1回目と2回目のけいれん時に
「自分はどう動けたのか」について振り返ってみます。
🔖1回目と2回目との比較
まず、明らかな違いは1回目よりも2回目のときの方が、けいれん症状が重く感じられたということです。
2回目の方が精神的な不安が大きかったということを念頭に振り返ってみます。
| 感情の動きと対応の有無 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 慌てることはなかったか | やや冷静を保てた | 1回目よりも冷静だった |
| けいれん時間の計測はできたか | 子どもから目を離せなかったため、できなかった | 1回目のときよりも状態が悪かったため、確認する余裕はまったくなかった |
| 体温測定できたか | 測り忘れていた | けいれん後、すぐは測れなかったが、のちに確認できた |
| 顔を横に向けて寝かせることはできたか | 心配するあまり、抱きかかえてしまった | 体のこわばりが1回目のときより強く、うつ伏せ状態であったため、抱きかかえてしまった |
| 服薬の判断、対処はできたか | 当日の夜は、医師の指示通り対応できた | 職場の医師に相談して、指示通り対応できた |

1度経験していたとは言え、いかに精神的な不安が強いのかが分かりました。「分かっていたのに動けなかったこと」も多く、自分でも悔しく感じています。
🔖反省点と改善点
2回目のけいれん時の反省点と解決案は、次の3つです。
- 「安静に」寝かせることができなかった
つらそうに苦しんでいる表情を見た途端、反射的に手が出てしまったのです。親としてはとても見ていられませんでした。
<解決案>
けいれん時の対応方法を、冷静なときに繰り返し確認しておく。 - けいれんの時間が計れなかった
<解決案>
けいれん時はパパが時間を見る、ママが体勢を確認するなど、事前に役割を決めておく。 - かかりつけの病院が「休診」という想定をしていなかった
<解決案>
相談先を、事前にリストアップしておく。
「休日診療所」や「小児救急電話相談(#8000)」、「民間のオンライン診療」など、いざというときの❝次の一手❞を調べておくだけでも、気持ちはぐっと楽になります。
実体験から学んだ「熱性けいれんに備える方法」とは?
熱性けいれんを体験して感じたことは、
「心の準備」と「意見を共有しておく」ことが大切になる
ということです。
親であれば、誰しも「子どもが健康でいてほしい」と願うものですよね。
そんな中、子どもがけいれんを起こせば、居ても立っても居られずに、パニックになってしまうでしょう。
だがらこそ、事前に万全な準備をしておくことで少し余裕の持った対応ができるようになるのです。
「うちの子だって発症する可能性がある」という心の準備をしておこう
「うちの子は大丈夫だよね?」
ではなく、
「熱が出たら、けいれんが起きるかもしれない」
という考え方を持ちましょう。
なぜなら、少しでもパニックにならずに対応できる可能性が高まるからです。
1度目の熱性けいれん時は、まさにパニック状態でした。でも、2度目のときは「また起きるかもしれない」と心構えがあったため、いくらか冷静に対応できたのです。
他人事ではなく自分事として、子どもを見守るようにしましょう。
夫婦間で役割分担を決めておこう
ママとパパで「役割分担」を念密に話し合って決めておきましょう。
なぜなら、一人がパニック状態になったとしても、もう一人が冷静に対処できる可能性もあるからです。
- もし、ひとりで看病しているときに熱性けいれんが起きたときはどうするのか?
- 熱が出たときは、いつまで自宅で様子をみるのか?
- 救急車を呼ぶタイミングはどうするのか、また二人で看病していたときにはどちらが呼ぶのか?
など、必ず意見を共有しておきましょう。
病院で聞くことを「リスト化」しておこう
「病院で聞かれそうな内容」をあらかじめリスト化しておくと、当日の受診の流れもスムーズになります。
動揺している中での病院受診。
冷静さを取り戻そうとしている中で、けいれん時の状況を説明することは思った以上に大変なことです。
突然の出来事にも慌てすぎずに対応できるよう、事前に「聞くことリスト」を備えておきましょう。

熱性けいれん時用のチェックリストを作りました。ご参考にしていただけると嬉しいです✨️
病院で問診される代表項目をまとめたチェックリストはコチラ(PDF)💡
熱性けいれんについて知っておきたいこと(参考情報)
熱性けいれんなど、子どもの体調に関する情報は「日本小児神経学会」や「日本てんかん協会」などのサイトをチェックしましょう。
また、子どもが体調を崩した時の相談や連絡、救急車を呼ぶ判断などについてもまとめてあります。
下記にリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてくださいね💡
📍熱性けいれんに関する公式サイト
【Q20:熱性けいれんはどのような病気ですか?|小児神経医がお答えします!小児神経Q&A|日本神経小児学会】
▶子どものけいれんに関する基礎知識や受診の目安がまとめられています。
【発作の介助と観察|日本てんかん協会】
▶専門家による啓発情報があり、家族として知っておきたいポイントが分かりやすく紹介されています。
📍子どもが体調を崩した時の相談方法に関する公式サイト
緊急医療相談、医療機関案内についての相談窓口はコチラ👇️
【救急安心センター事業(#7119)ってナニ?|救急車の適時・適切な利用|総務省消防庁】
▶「救急車を呼ぶべきか、今すぐ病院に行ったほうがいいのか」迷ったときの判断ポイントが載っています。

「救急安心センター事業」っていう制度に参加している都道府県・政令市などが使える番号だよ。利用できるかどうかは、お住まいの都道府県・市町村の公式サイトで確認しよう!
家庭での対処法や受診の必要性を相談できる窓口はコチラ👇️
【(子ども医療電話相談事業(#8000)について|厚生労働省】
▶子どもの急な発熱や嘔吐、腹痛などの症状が出たときに相談できる番号です。

日本全国統一の短縮番号だよ。休日・夜間で、子どもが急に体調が悪くなったときの症状等を相談できるよ。
我が家からのメッセージ
この経験は、❝我が家だから起きたこと❞かもしれません。
でも、子どもの急な発熱やけいれんは誰にでも起こりうることだと思います。
だからこそ、
「迷ったら、医療機関や相談窓口に連絡を検討する」
そんな選択肢を、少しでも頭の片隅に置いてほしい。
そして、
「もしかしたら我が子も発症するかもしれない」と、事前に心の準備をしておいてほしいと切に思っています。

他にも子育てが少しラクになるヒントを発信しています。ぜひご覧になってみて下さいね✨️
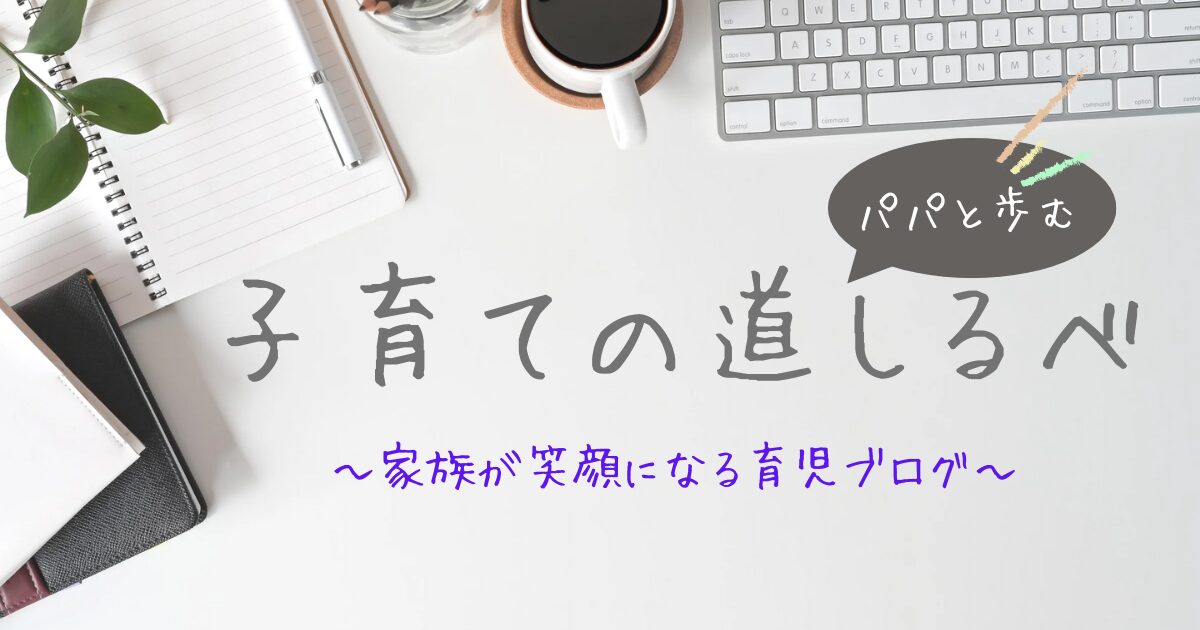
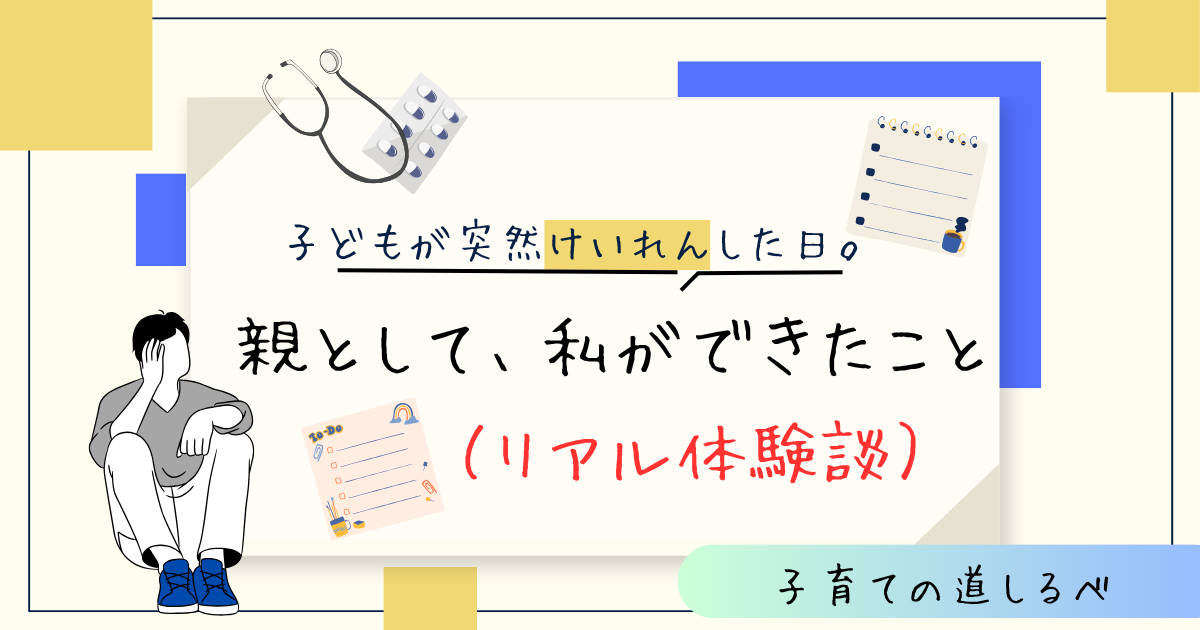
-1024x538.png)
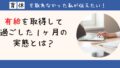

コメント