「無理に育休を取らなくて大丈夫だからね」
不安そうな表情で、妻からそう言われました。
正直、「育休を取得するかどうか」私の心は乱れ続けていました。
でも、今だからこそ自信を持って言えることがあります。
それは、「とにかく、家族のそばにいる時間をつくってほしい」ということ。
もし、育休を取得するか迷っているのであれば、ママや赤ちゃんのためにも一歩踏み出してほしいのです。
実際に、赤ちゃんと一緒に過ごしたあの「1ヶ月間」は、私の人生を大きく変えました。
この記事では、
「育休を取得したい」けど迷っている方へ向けて、
- 育休制度の基本について
- 育休を取得できなかった理由
- 有給を取得して休暇に当てた理由
- 実際に、休んで得られたもの
- 復帰後の職場の雰囲気
- 反省点と学んだこと
について、
実体験談を交えたエピソードを紹介します。
今しか取ることが出来ないチャンスです!
この記事を読んだあとで、少しでも、あなたの背中を押せたら嬉しいです。
🖊️この記事で分かること
育休は、積極的に取得しよう

家族のために、一歩踏み出しましょう。
職場の目、人事の評価などを悩むかもしれません。
でも、たくさん葛藤して悩み続けて、
挙句の果てには「育休が取れずに有給を取って休む」という異例の決断をした私だからこそ自信を持って言えます。
「ぜひ、取得してください!(笑)」
なぜなら、「その時間は、必ずこれからの人生を大きく変える、かけがえのないものになる」からです。
なぜ、育休は取得した方がいいのか?

理由は2つあります。1つは、
育休と取得できるチャンスは「今」しかないから。
育休は、「子どもが生まれる」という限られた期間しか利用できません。
せっかく利用できる制度があるのですから、ぜひ活用しましょう。
2つ目の理由は、
「育児と家事の両立が、いかに過酷であるか」体感できるから。
育休を取得すれば、育児と家事を両立することが、いかに大変であるか体感できます。
そして、仕事へ復帰した際に「ママがいかに過酷な環境で頑張っているのか」が分かるのです。
「家庭を回すのはママだけではなく、夫婦二人で回すことが重要なんだ」と気づけるようになります。
育休制度とは何か
育休制度とは、育児のため一定期間仕事を休むことができる制度です。
男女ともに取得可能で、法律上も会社側に取得を拒否する権限はありません。
育児・介護休業法では、
原則として「子どもが1歳になる前日まで取得できる」と定められています。
また、1歳時点で保育所に入れないなど特別な理由がある場合、最長2歳までの延長申出可能です。
育休取得のメリット
メリットとしては、
- 子どものそばで、成長を見守れる
- 育児と家事の分担がしやすくなる
- 育児の大変さを実感することで、家族への理解が深まる
- 育児休業給付金など、公的なサポートを受けることができる
などがあります。
つまり、公的な費用サポートを受けつつ「家族のことに集中できる時間」を得ることができるのです。
育休取得のデメリット
デメリットとしては、
- 職場への相談や雰囲気に抵抗を感じることがある
- 収入が一時的に減る(育児休業給付金は全額ではない)
- 育休明けの業務復帰に、不安を感じることがある
- 男性が少ない職場では、周囲との温度差に悩むこともある
などがあります。
つまり、育休取得の前後で心理的な抵抗が大きいのです。
男性の育休取得率は、近年増えてきている
厚生労働省の調査によると、男性の育休取得率は、
令和4年度:約17.1%
令和5年度:30.1%
▶調査開始以来、初の30%超え
令和6年度:40.5%
と、漸増しています。
つまり、「育休を取得しよう」という気持ちのある男性が少しずつ増えてきているのです。

「実際に取得している男性が増えている」という結果は、とても心強いですよね。
【参考:「令和6年度雇用均等基本調査の結果概要|厚生労働省】
育児休業給付金が支給される
育休を取得した場合、雇用保険に加入している人で一定の条件を満たせば、育児休業給付金が支給されます。
ただし、「全額補償」ではありません。
賃金日額よりも少ない給付額となります。

私は有給休暇を取得したので、賃金がそのまま支給されました。
育休を取得するためには、早めの申請が必要となる
育休は、法律上「育休を始めたい日の原則1ヶ月前までに申し出る」ことになっています。
他にも、出産予定日よりも早く赤ちゃんが生まれた場合等は、休業開始予定日の繰り上げ変更をすることもできます。
取得するに当たっては、
- 上司や同僚とスケジュールを調整する
- 業務の引き継ぎをする
- 「急に言われても困る」という反応を防ぐ
などの事前準備もありますので、やはり早めの申請を行うようにしましょう。

出産予定日のおよそ2ヶ月前くらいから余裕をもって相談を始めておきましょう。
🔖育休申請までのフロー(例)
- 妊娠初期〜中期
ママの体調が比較的安定している時期です。「育休」の話題を出してみましょう。 - 妊娠後期(28週〜)
育休の検討を本格的にスタートしましょう。この時期に、上司や人事にも相談をしておきましょう。 - 出産予定の1か月前
法律上の「申請リミット」です。 この時期を過ぎると、申請が間に合わない可能性もあります。 - 出産へ
事前に準備が整っていれば、スムーズに育休期間へ突入です!
このフローはあくまで目安ですが、
やはり早めの行動がカギになるでしょう。
【失敗談】なぜ、育休が取れなかったのか
理由はシンプルです。それは、
「妻の近くにいたい」けど、会社の評価を気にして決心が付かなかったから。
育休のことは頭の片隅にはありました。
でも、当時はずっと迷っていたのです。
理由①職場の目を気にしていたから
うちの場合、男性が少ない職場だったので、育休を申し出ることも大きなハードルでした。
法律上、会社側は取得を拒否する権限はないけれど、育休を取得することで、
「職場の雰囲気が悪くなったらどうしよう」
「休んだら評価が下がるんじゃないか」
など、「職場の目」や「評価」を気にしてしまったのです。
理由②気持ちの整理ができず、育休の申請が遅れたから
もちろん、パパとして、
「妻の負担を減らしたい」
「赤ちゃんが生まれてくる瞬間に、そばにいたい」
という気持ちもありました。
でも、仕事に対する不安な気持ちの整理ができず、時間だけが過ぎていってしまったのです。
結局、「休みを取ろう」と決断したのは、出産が間近に迫った頃でした。法律上の申請リミットを超えてしまったのです。
なぜ、有給を取得しようと思ったのか
それは、
「そばにいたい」という思いが強くなったから。
家庭の空気は、日に日に張り詰めたものへと変わっていく。
どれだけ励ましの声をかけても、どこか孤独を背負っているようにも見えました。
当時はコロナ禍でもあったため、
立ち会い出産は叶わず、病院で妻ひとりで不安と戦うことになることも分かっていました。
そんな中――
「無理に育休を取らなくて大丈夫だからね」
と妻から言われたのです。
その瞬間、決意が固まりました。
「パパとして、何ができるか分からない」
「でも、そばに居ることで二人を助けることができるのではないか」
「どんなかたちでもいい。家族で過ごす時間が大切だ」
そう確信して、「有給を使ってでも、家族との時間をつくる」と心に決めたのです。
🔖余談:病院での、ママ同士の会話
出産後、妻から興味深い話を聞きました。
入院中に知り合った妊婦さんと、
「私の主人も職場に無理を言って、休みを取ったんです。本当に安心しました」
こんな話をしていたそうです。

やはり、「パパがそばにいること」は、本当に心強くて、ホッとできるようです。
失敗談を通して伝えたいこと
できるだけ早く相談しよう!
なぜなら、相談をすれば、
- 選択肢が増える
- 心の負担が減る
- 先輩たちの意見が聞ける
といったメリットがあるから。
休み方は一つではありません。
でも、そばにいられる時間は「有限」です。
後悔しない選択をするためにも、早めの相談をしましょう。
育児のために、「1ヶ月」を有給にあてて実感したこと
休暇前に抱えていた「悩みごと」は消えた。
仕事への不安は、頭から消えた
正確には考える余裕すらありませんでした(笑)
なぜなら、
目の前には、泣き止まない小さな命と、それを支える妻がいて、「自分がどう動くかで家族の空気が変わってしまう」と体感できたから。
慣れないミルク、夜泣き、オムツ替え、沐浴、そしてまたミルクなど――
気付いたら、あっという間に一日が終わってしまうのです。
他のことを気にしている余裕は、まったくありませんでした。
有給を取得して「正解」だった
妻の気持ちに寄り添って正解でした。
なぜなら、「一人で家事と育児を両立させることは過酷である」と実感できたから。
出産後のママは、心も体も限界であり、圧倒的なハンデを背負っています。
だからこそ、パパがいるだけでママの負担はかなり軽減できます。
そして、いよいよ職場に復帰――
ただ、久々にスーツを着て、職場に向かう私はどこか落ち着かない気持ちでした。
復帰後の職場と、そこからの関係
復帰後の職場は、正直言うと少し空気が悪かったです。
挨拶を交わす上司や同僚の表情が、どこかよそよそしいような…そんな空気がありました。
でも、それは事前にしっかり話し合いをせず、突然のような形で休みに入ってしまった――
そんな自分自身の不手際が原因だったと思います。
「あのときちゃんと伝えていれば」
何度かそう思ったこともありました。
けれど、あれから4年。
今では、子どもの話で自然と盛り上がることも増えました。
急な体調不良で休むときも、「大丈夫?」と気遣ってもらえるようにもなりました。
「最初から敵だったわけじゃない。きちんと話せば、理解は生まれる」
この経験があったからこそ、そう思えるようになりました。
-150x150.png)
子どもと過ごせる時間は”今”しかありません。
家族とどう向き合うか――それは、自分の生き方そのものに関わってくる。
休暇を取ってみて、ようやくその意味を肌で感じることができた気がします。
これからパパになるあなたへ
▶使える制度は「今」しかない!
迷っているなら、一歩踏み出してみてください。
「制度がある人」は迷わず使ってください。
「制度がない人」も、どうか”できること”を見つけてみてください。
私も悩んだし、決して勇気があったわけではありません。
でも、あのとき「休もう」と決めた自分を、今では誇りに思っています。
必ず、その時間は”これからの人生を多く変える、かけがえのないもの”になります。
▶「できることを選んで」行動しよう
「会社には制度がないから”諦める”」ではなく、
「今できる方法を探す」ことが、家族との時間を守る第一歩です。
仕事は代わりがいても、
”今この瞬間の家族との時間”には、代わりがいません。
あの1ヵ月で、私の中の”育児感”は大きく変わりました。
そして何より、「家族になる」ってこういうことかもしれない――そう思えた日々でした。
育休でも、有給でも、あなたにできる範囲で構いません。
大切なのは、そばにいる「時間」を選ぶこと。
その選択が、きっとあなたと家族のこれからを支えてくれます。
「育休は取れなかったけれど、それでもできることはある」
そんな想いが、これからパパになる誰かの心に届きますように。
-150x150.png)
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
パパとしての一歩を踏み出す方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです✨️
🔗「これからパパになるなんて、まだ実感がわかない…」
そんな風に感じていた頃の、私の正直な気持ちの体験談はコチラ👇️
【関連記事:【実体験】パパになった日。私が”父親”を自覚するまで | 子育ての道しるべ】
🔗「子どもが生まれる前に、どんな準備をしておけばいいの?」
そんな”これからパパになる方へ”向けた記事はコチラ👇️
【関連記事:【パパになる前に】妊娠・出産・育児で知っておきたいこと | 子育ての道しるべ】
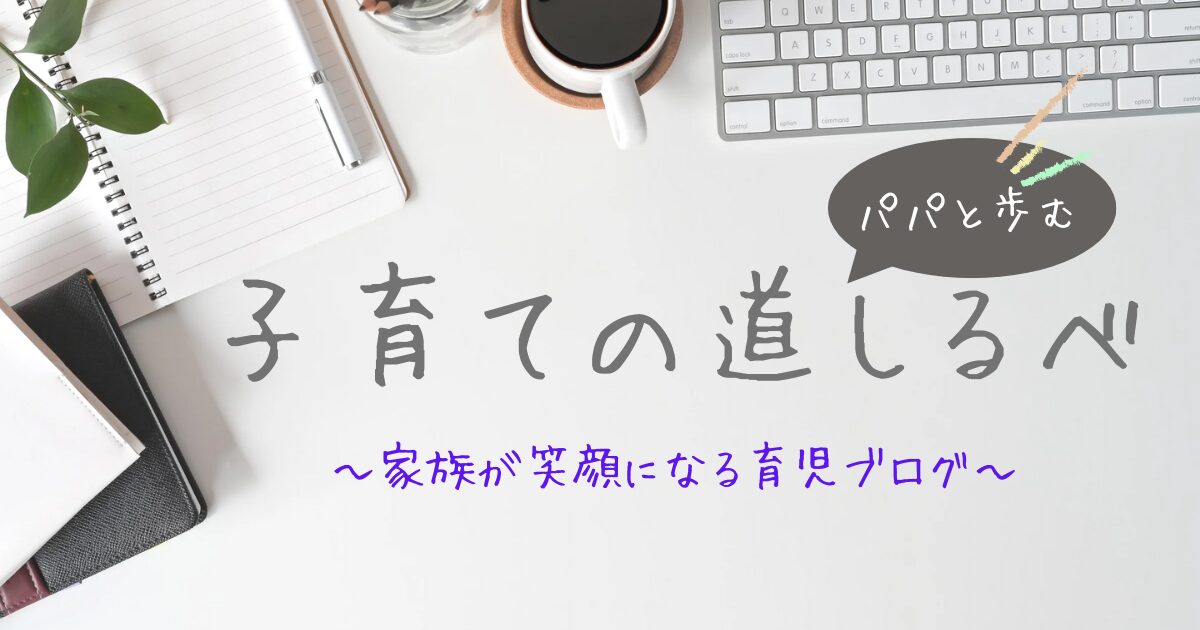
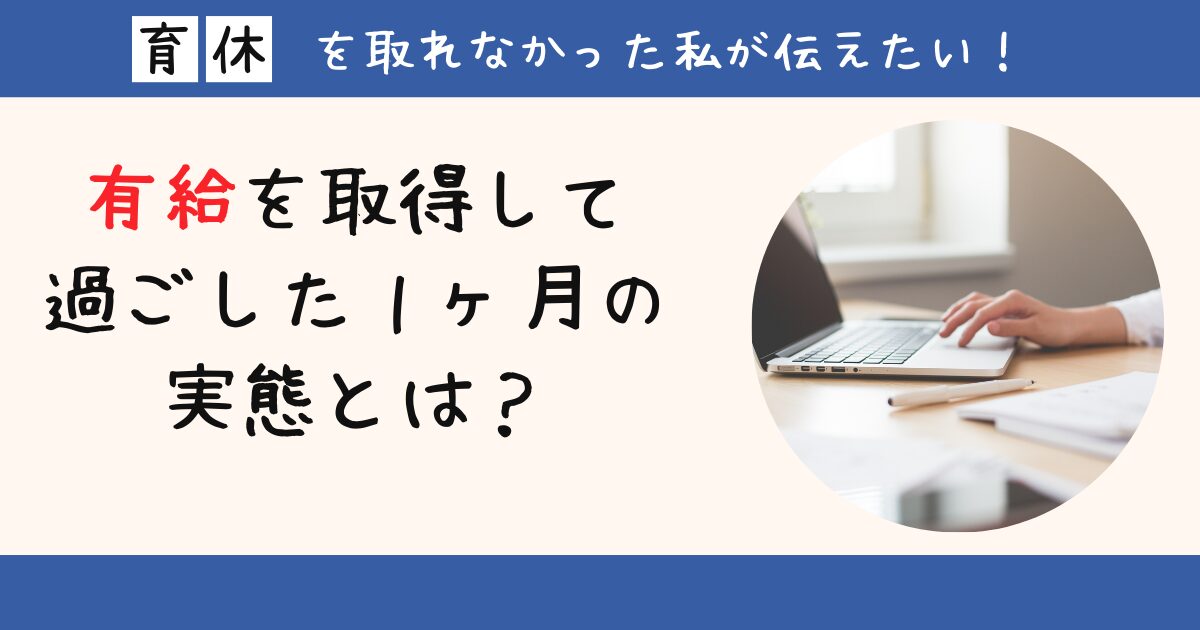


コメント